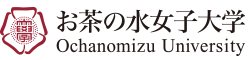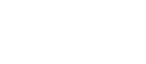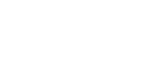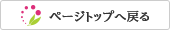ページの本文です。
「みらいの扉キャンプ2025」を開催しました
2025年8月29日更新
国立大学法人東京科学大学、国立大学法人お茶の水女子大学、国立大学法人奈良国立大学機構奈良女子大学は、日本の未来を担う卓越的理工系女性人材の発掘と育成を目的として、理工系に関する学びの実体験を通して未来のキャリアを想像するプログラム「女子STEAM生徒の未来チャレンジ」を実施しています。
2025年8月6日~8日の3日間、同プログラムの一環として、お茶の水女子大学を会場に「みらいの扉キャンプ2025」が開催されました。
全国の学校から推薦・選抜された高校1、2年生の女子生徒50名を対象に、2泊3日の合宿形式で、先進理工学講義、ものつくり実習、物理化学実験、社会課題解決ワーク・アイデアコンテスト、女性キャリアパス講義、未来を語る座談会等を実施しました。
なお、本プログラムは、一般財団法人三菱みらい育成財団の助成を受けて実施いたしました。
【みらいの扉キャンプの詳細】
「みらいの扉キャンプ2025」
https://www.e.titech.ac.jp/mirai-challenge/mirainotobira-camp/
【期間中の様子】
(1日目)
午前中に会場(お茶の水女子大学)に到着した参加者は、食堂で昼食をとり、午後からの開講式に出席しました。
開講式では、東京科学大学荒木稚子教授の進行のもと、お茶の水女子大学佐々木泰子学長、奈良女子大学高田将志学長より挨拶が述べられました。
佐々木学長は挨拶の中で、かつて男性が中心であったSTEAM分野に女性が参画することによって大きな変化が生まれることが期待されていること、社会を変革するイノベーションにも女性の進出が求められていることなどに触れ参加者への応援メッセージを贈りました。
続いて、プログラム代表の東京科学大学岩附信行特命教授より、「女子STEAM生徒の未来チャレンジ」について、背景や内容の説明が行われました。
説明では、日本のジェンダーギャップ指数や世界の大学学部理工系入学生における女性割合などの現状を踏まえ、社会課題の解決やイノベーションの創出には女性をはじめ社会を構成する多様な視点が必要不可欠であることなどに触れながら、プログラム全体の実施内容について、3日間の期待と抱負が述べられました。
その他、1日目には、お茶の水女子大学伊藤貴之教授による「情報科学で音楽を眺める」、奈良女子大学久保博子教授による「暑さ寒さを計測し、生活を見守るデザイン」の先進理工学講義のほか、奈良女子大学下村真弥准教授によるキャリアパス講演などが行われました。
(2日目)
希望者ごとに分かれ、午前・午後にそれぞれ実習を行いました。
お茶の水女子大学大瀧雅寛教授による「水を透明にするには~水の高度浄水処理~」では、参加者たちがグループに分かれ、高校の授業では使ったことのない実験器具を用いるなどして、浄水処理に挑戦しました。参加者たちは、初めて手に取る実験器具に目を輝かせ、使い方を真剣に聞き丁寧に扱いながら実験を行う様子が見られました。
その他、「宝石 × 工学 2025: 作る・壊す・発電する」荒木 稚子 教授(東京科学大学)、「虹色の花を咲かせよう!植物が水を吸う仕組み」奈良 久美 准教授(奈良女子大学)、「機能性ハイドロゲル材料を体験してみよう!」秋元 文 准教授 (お茶の水女子大学)、「振動を利用して走る移動機械の設計・試作・競争」岩附 信行 特命教授(東京科学大学)、「Python で時系列データを可視化しよう」瀬戸 繭美 准教授(奈良女子大学)の実験・実習が行われました。
また、AIST Solutionsの大石佑子氏によるキャリアパス講演も行われました。
(3日目)
午前には社会課題解決コンテストが開催されました。グループに分かれて事前に考えてきた社会課題とその解決策について意見交換を行い、発表資料を作成しました。限られた時間の中で、高校生ならではの柔軟な発想や新たな視点を含む、さまざまな課題解決策が話し合われました。その後、審査員によって選ばれた4グループが全員の前で発表を行い、質疑に答えました。時折、即座に回答することが困難な質問にも、チーム内で協力しながら真摯に考え、回答する様子が見られました。
午後には閉校式が行われ、東京科学大学の大竹尚登理事長から、参加者及びプログラムの運営にかかわった関係者に向けた労いの言葉が寄せられました。その後、3日間同行した関係の先生方からの講評があり、すべてのプログラムを終了しました。
プログラム終了後には、希望者にお茶の水女子大学、東京科学大学の研究室見学会が実施され、全日程を無事に終了いたしました。